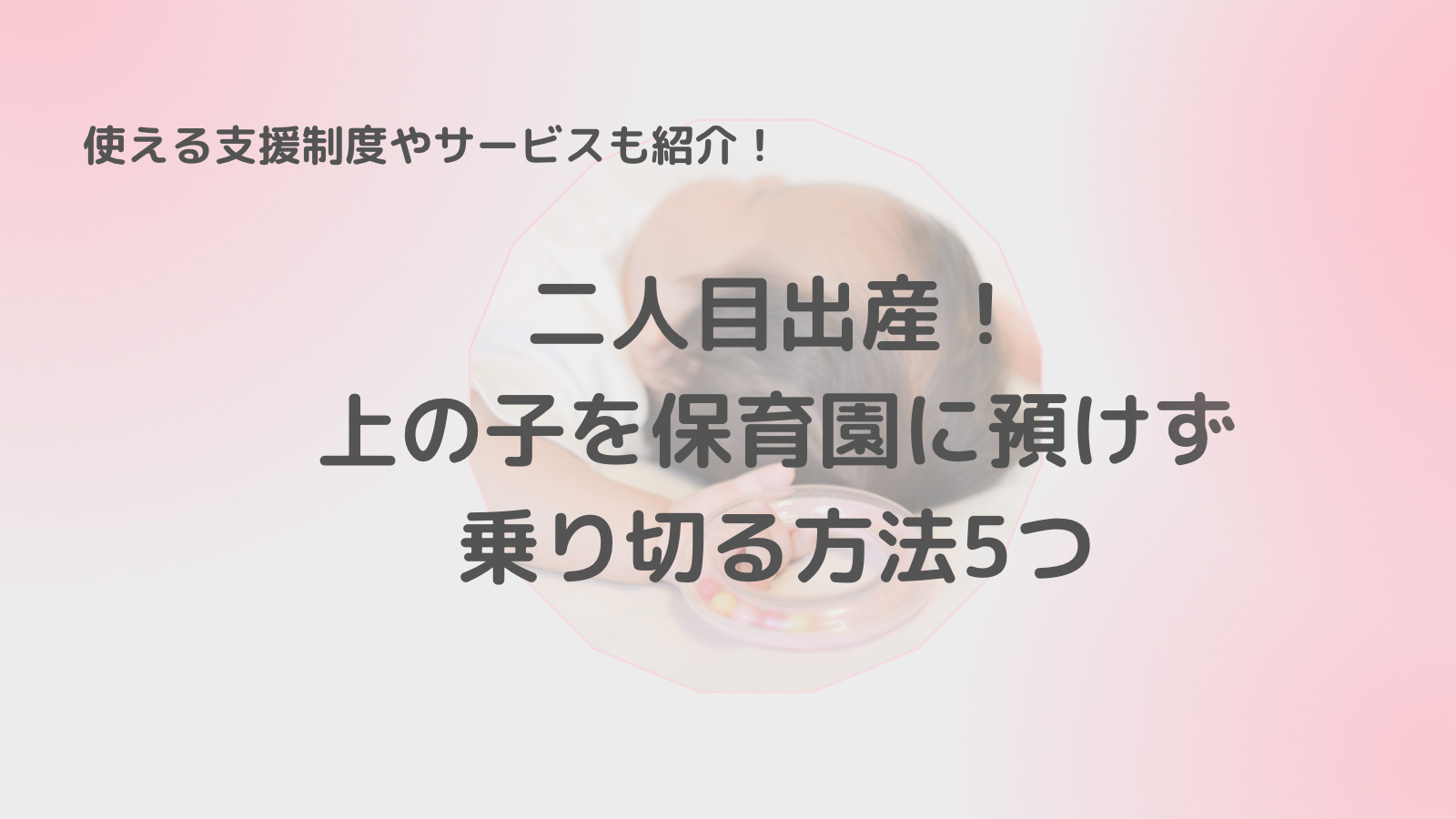こんにちは、育休中ママのみゆです。
2人目を妊娠、出産!
とてもうれしいことなのですが、1人目の時とは違う悩みが出てきますね。
その1つが「上の子のお世話をどうするのか」問題。まだ保育園に行っていない場合は特に大変ですね。
産前産後だけでも認可保育園に入園できればいいのですが、保育園激戦区や年度途中では「妊娠・出産」の要件では入れない…ということも少なくないようです。
私も1人目の育休中に2人目を妊娠、続けて産休育休に入ることになり、上の子のお世話をどうしようか本当に悩みました。
今回は、上の子を保育園に預けずに乗り切る方法5つについてまとめました。
- 二人目出産後、上の子のお世話をどうしようか悩んでいる…。
- 産前産後の保育園に預けたいけど預けられない…。どうしたらいいの?
- 保育園に預けずに2人とも家で見たいけれど、やっていけるか心配…。
そんな方に、どんな方法や支援制度があるのかをご紹介します。

いろいろな方法を知ることで、「なんとかなるかも…!」と少しでも不安や心配が減ればうれしいです。
産前産後の保育園利用については、こちらの記事で紹介しています。
パパが育休をとる

まずは「パパが育休をとれないか」ということは一度検討してみてほしいです。
メリット
〇 パパに24時間体制でサポートしてもらえる
〇 パパにも主体的に育児に参加してもらえる
〇 上の子にとって環境の変化がない
パパに育休をとってもらえると、ママにとっては何より強力なサポートになります。
上の子もいつも一緒にいるパパに見てもらえるので安心ですね。
一方で、もちろんデメリットもあります。
デメリット
× 収入が減少する
× そもそも育休が取れるのか、希望の期間取得できるかわからない
× 産前のサポートは難しい
男性が育休を取得しても、女性と同様に「育児休業給付金」という手当が支給されます。
育児休業給付金といっても、働いてもらえる給料に比べるとだいぶ少ないんじゃないか…と思う方もいますが、手取り賃金で比較すると育児休業前の約8割程度になる方が多いようです。
とはいえ収入が減少することには変わりないので、家計管理は必要になってきますね。
また2021年発表の厚生労働省の調査で、男性の育休取得率は12.65%とまだまだ低いのが現状です。
パパの仕事や職場の環境により大きく異なるので、まずはパパと育休取得について相談してみることをおすすめします。
実家(義実家)のサポートを受ける

おばあちゃんやおじいちゃんは子育ての経験もある頼れる存在ですね。
上の子と一緒に里帰りしたり、おばあちゃんに家にきてもらうといった方法があります。
メリット
〇 産前~産後まで、家事全般・上の子のお世話も頼める
〇 上の子がおばあちゃんやおじいちゃんに慣れていれば、上の子にとっての変化も少ない
デメリット
× おじいちゃん・おばあちゃんが仕事をしていたり、高齢な場合、受けられるサポートに限界がある
× 里帰りした場合、パパが育児に参加する機会が減る
サポートを受けられる場合、特に産後はありがたく頼らせてもらいましょう。
実家のサポートを受けつつ、手がたりない時には下記の支援制度も利用できるといいですね。
一時保育を利用する

地域の子育て支援センターや一部の認可保育園で実施されており、事前の登録・予約が必要です。
参考までに、私の地域の認可保育園で実施されている一時保育の内容です。
時間 : 平日 9:00~17:00(時間は応相談)
料金 : 1時間500円、給食を利用する場合+200円
料金については、認可保育園では500~600円程度が相場のようです。
一時保育のメリット、デメリットについては以下の通りです。
メリット
〇 事前に登録しておけば産前から利用することが可能
〇 利用料金は他と比べて最も安い
デメリット
× 事前に書類の提出が必要なことが多く、利用開始までに時間がかかることも
× 事前予約が必要なため、希望する日時で予約が取れない可能性もある
予約をとることができれば、保育士さんなど専門の方に見てもらえるので親としては安心ですね。
ファミリーサポートを利用する

ファミリーサポートとは、地域において育児の援助を受けたい人(依頼会員)と行いたい人(提供会員)が有償で助け合う会員組織のことです。
事前に登録を行うことで、提供会員から育児の援助を受けることができます。
提供会員になるには特別な資格は必要ありませんが、援助活動に必要な講習を受ける必要があります。
子どもを預かってみてもらう場合、場所は提供会員の自宅や地域の子育て支援センターや児童館など、地域によって異なります。
利用料金は、私の住む地域では1時間700円~でした。交通費や食費は別途かかることが多いようです。
ファミリーサポートのメリットやデメリットは以下の通りです。
メリット
〇 事前に登録しておけば産前から利用することが可能
〇 提供会員は地域の子育て経験者が多く、ママの話し相手や相談相手になってもらえることも
〇 民間のサービスに比べると利用料金は安い
デメリット
× 全国的に提供会員数が少なく、自治体によっては予約が取りづらい
× 顔合わせや打ち合わせが必要で、利用までに時間がかかることも多い
一時保育やファミリーサポートの内容は自治体によって異なるので、気になる方はお住いの自治体のホームページなどで確認してみてください。
シッターサービスを利用する

民間のサービスで、自宅に来て子どもをお世話をしてもらうことができます。
ベビーシッターには特別な資格は必要ありませんが、保育士・幼稚園教諭や学校の先生・看護師など、子どもと関わる資格を持った方も多いです。
利用料金は、私の住んでいる地域周辺では1時間1500~1600円程度で、別途交通費がかかります。
ベビーシッターサービスのメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
〇 当日や前日の予約でも利用が可能
〇 地域の支援制度と比べて予約が取りやすく、時間なども柔軟に対応してもらえる
〇 自宅に来てもらえるので、送迎の手間がかからない
デメリット
× 地域の支援制度と比べ、料金が高い
シッターサービスはネットで予約をとることができ、希望に合ったシッターさんを紹介してもらえるマッチングサービスもあります。
気になる方は一度検索して調べてみてください。
まとめ:いろいろな支援を利用して、二人目出産を笑顔で迎えよう
以上、上の子を保育園に預けずに乗り切る方法5つについてご紹介しました。
- パパが育休をとる
- 実家(義実家)のサポートを受ける
- 一時保育を利用する
- ファミリーサポートを利用する
- シッターサービスを利用する
それぞれにメリットとデメリットありますが、どれか一つだけでなくいろいろな方法を組み合わせて、ママの負担を少なくし、家族が笑顔で過ごせるといいですね。

ご覧いただきありがとうございました!