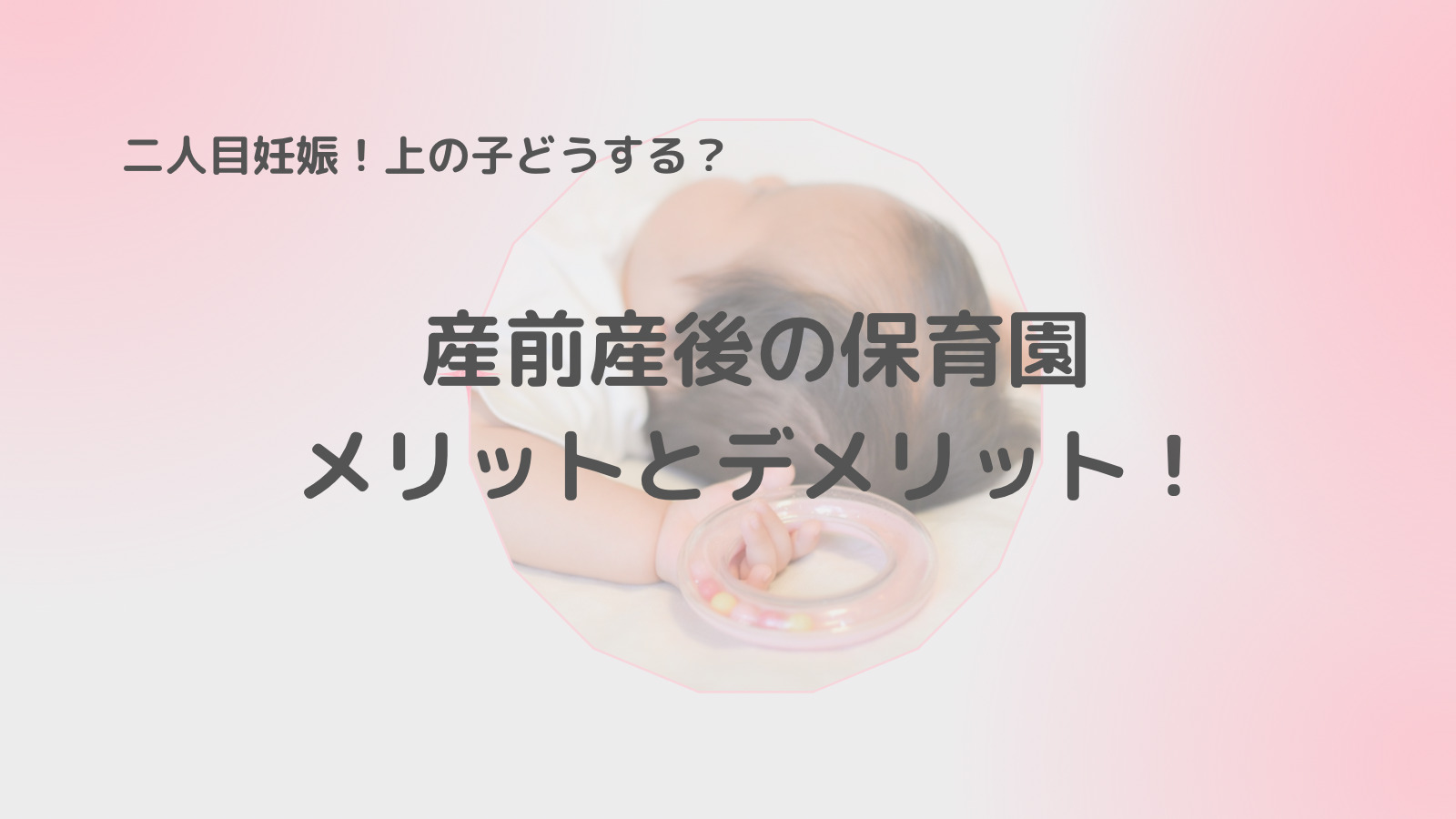こんにちは、育休中ママのみゆです。
二人目の妊娠!
とてもうれしいですが上の子がまだ保育園に行っていない場合、お世話をどうしようか悩みますよね。
私も一人目の育休中に第二子を妊娠、そのまま続けて二人目の産休育休に入ることになり、産前産後上の子のお世話をどうしようか本当に悩みました。
現在では「妊娠・出産」は保育を必要とする事由として認められており、産前産後は保育園を利用することができます。
この記事では、産前産後の保育園利用の基本情報、利用するメリットとデメリットを解説します。
私が悩みに悩んでいろいろな人(保育士さんや助産師さん)に相談したり先輩ママの体験談を聞いて、いろいろな視点から得た情報です。
メリット・デメリット両方を理解すると判断もしやすくなりますね。

産前産後保育園を利用しようか悩んでいるパパママの参考になれればうれしいです!
産前産後の保育園利用の基本情報

利用制度
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、保育が必要とする事由として「妊娠・出産」が認められています。
そのため専業主婦や育休中など、仕事をしていなくても認可保育園に預けることができます。
妊娠・出産が事由の場合、原則として「保育標準時間」での利用ができます。
・「保育標準時間」=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
よくわかる「子ども・子育て支援新制度」:子ども・子育て本部-内閣府
・「保育短時間」=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
※以降認可保育園のことを「保育園」と記載しています。
利用期間
産前産後にどれくらいの期間、保育園に預けることができるかは自治体によって異なります。
参考までに、私の住んでいる地域では利用できる期間や時間は以下の通りでした。
・産前2か月~産後2か月:標準時間
・産後3か月から産後6か月:短時間
産前2か月~産後2か月程度預けられる自治体が多いようですが、詳しくは各自治体のホームページを見たり、市役所に連絡して確認してみてください。
保育料
現在3歳から5歳の子どもは保育料が無償化されていますが、0歳から2歳の子どもは保育料がかかります。
保育料は父母の市町村民税所得割、つまり世帯収入に応じて設定されます。
参考までに私の住んでいる地域では、世帯年収500万円で月4万円程の保育料がかかります。
保育料の設定も自治体によって大きく異なるので、気になる場合は各自治体に確認してみてください。
ママにとってのメリット

それでは産前産後に保育園に預けるメリット・デメリットについて、
- ママにとってのメリット/デメリット
- ママと子ども両方にとってのメリット/デメリット
この4つに分けて解説します。
①預けている間、ある程度体を休められる
出産でダメージを受けた体で、生まれたての赤ちゃんと上の子両方のお世話をするのは大変ですね。
産後1か月程度は無理をせず、赤ちゃんのお世話が中心の生活をするように産院からも説明されます。
上の子が保育園に行っていれば、その間下の子と一緒に昼寝をするなど体を休めることができます。
産前にも預けることができれば、大きなお腹でしんどい時にも少し休むことができますね。
②下の子のお世話の時間が確保できる
2人を同時に見ていると、もうある程度意思表示ができるようになっている上の子を優先しがちになります。
特に新生児の時期は頻繁に授乳やおむつ替えをする必要があるので、上の子が保育園に行っている間だけでも、下の子だけを集中してみてあげられる時間があるのは貴重ですね。
③一旦通い始めても、何かあれば休ませる等自由に使える
保育園に通い始めたら、絶対に毎日通わなければならないというわけではありません。
通い始めてみてやっぱり家で二人とも見たほうがよさそうだと思ったら、休ませたり早めに迎えに行ったりと自由に使えます。
保育園に預ける選択をしても、やっぱり預けてみて問題がありそうだったら預けないという選択もできます。
その逆で、預けないという選択をしたけれど、やっぱり預けたいという選択はできませんね。
ママと子ども両方にとってのメリット

①保育園での集団生活が子どもの刺激になる
保育園に行き始めた時期はもちろん子どもは大泣きすると思います。
ですが保育士さんに聞いていると、子どもの適応力はとても高く、だいたいの子が1か月程度で慣れて泣かなくなるようです。
保育園では同年代の友達や先生と交流できますし、家ではなかなかできないような遊びもたくさんしてくれます。
通っている間にトイレトレーニングを進めてくれることもあり、子どもの成長につながります。
②生活が規則正しくなる
自宅で過ごしていると、起きるのや寝るのが遅くなったりと生活リズムが崩れがちです。
保育園に通っていると登園時間が決まっているので、必然的に朝早く起きることになります。
朝早く起きるので、自然と夜寝るのも早くなっていきます。
保育園でも昼食やお昼寝など決まったリズムで生活するので、生活リズムが整えやすくなります。
③保育園が上の子の安心できる場所になることも
これは私も助産師さんに教えてもらって初めて気づいた視点です。
下の子が産まれるということは、上の子にとっても大きな変化です。
里帰りもする場合は、普段生活する環境も変わりますね。
赤ちゃんという知らない存在が突然現れて、ママも今までと違ってその突然現れた存在につきっきりになってしまっている。家もいつもの場所と違う。
そんな中で保育園は友達も先生も変わらない。そんな変わらない場所があることに上の子は安心することもあるようです。
④次に保育園や幼稚園に入園する際の適応が早くなる
産前産後は期間限定の利用ですが、いつかまた保育園や幼稚園に入園する日がくると思います。
数か月の間でも保育園に通っているとそこがどういう場所かわかっているので、初めて通い始める子よりも適応できるのが早くなります。
ママも一度経験があるので、保育園デビューがスムーズにできたという声もありました。
ママにとってのデメリット

①保育料がかかる
基本情報でもお伝えしましたが、0~2歳の子どもを預ける場合には保育料がかかります。
産前産後の保育園を利用するということはママは専業主婦や育休中など働いていないことが多いため、保育料が家計に与える影響も大きくなりますね。
②下の子を連れての送迎が大変
下の子がまだ生まれたての新生児期、ママも産後1か月程度は外出せず家の中で過ごすことが望ましいです。
1か月を過ぎてからでも、まだまだ首も座っていない下の子を連れての送迎は大変です。
保育園に入園させる場合には、保育園の送迎をどうするのか検討しておく必要がありますね。
パパやおじいちゃん・おばあちゃんにお願いしたり、ファミリーサポートなどの子育て支援を利用する方法もあります。
③預けることに罪悪感や後ろめたさを感じてしまうことも
世の中にはいろいろな考え方の人がいて、上の子だけ保育園に預けるということを「上の子だけかわいそう」と言われてしまったママもいるそうです。
周りに保育園に預けず2人育児を実際にしているママ友がいれば、自分は預けていいのか?と迷ってしまうこともあります。
ママ自身にも迷いがあって上の子に申し訳ないという気持ちを持っていると、預けることが辛くなってしまうこともあるようです。
個人的には、保育園に預けることが「かわいそう」「甘え」では決してないと思いますが…。
ママと子ども両方にとってのデメリット

①感染症にかかるリスクがある
初めて集団生活をする場合、まだウイルスに対する抵抗力の弱い子どもは病気をもらってきやすいです。
いわゆる保育園の洗礼です。
実際に通わせていたママの中には、風邪を引いて治っての繰り返しで期間の半分程度しかちゃんと通えなかった…という声もありました。
どの程度病気にかかるかはその子どもや、感染症が流行しやすい季節かどうかによっても異なると思いますが、ある程度の「保育園の洗礼」は覚悟しておく必要があります。
自分も臨月だったり新生児がいると、周りにうつらないように配慮も必要になってきます。
②子どもが保育園に慣れてきた頃に退園しなければならない
産前産後の保育園利用は期間が決まっており、その期間が終われば退園することになります。
子どももやっと慣れてきて、友だちと一緒に楽しく通っていたとしても退園せざるを得ません。
子どもがどう感じるかは様々だと思いますが、親としてはつらいところがありますね。
③上の子が不安定になることも
これも子どもによって反応は大きく異なると思いますが、中には夜泣きがひどくなったり、赤ちゃん返りのようになったりする子もいるそうです。
赤ちゃん返りについてはちょうどイヤイヤ期と重なることも多く、どこまで保育園の影響といえるかはわかりませんが、ママとしては「保育園が子どもの負担になっているのかな…」と不安に思ってしまうこともあります。
まとめ:ママやパパが笑顔で育児できる選択をしよう
以上、産前産後の保育園利用のメリット7つとデメリット6つを解説しました。
メリットとデメリット両方を理解したうえで納得できる選択をしていきたいですね。
私がいろいろな方から話を聞いて、判断する際のポイントにしてほしい点は次の2つです。
・子どもの適応力をなめたらあかん!
・ママやパパが笑顔で育児できる選択をする
ちなみに、我が家ではパパが育休をとれることになり産前産後の保育園は利用しませんでしたが、育休がとれなければ利用していたと思います。
「子どものためにこうするべき」「親ならこうあるべき」という思いや周りの声にとらわれず、それぞれの家庭の状況に合わせてベストな選択をしていけるといいですね。
産前産後の保育園の利用に悩んでいる方の参考になればうれしいです!

ご覧いただきありがとうございました♪