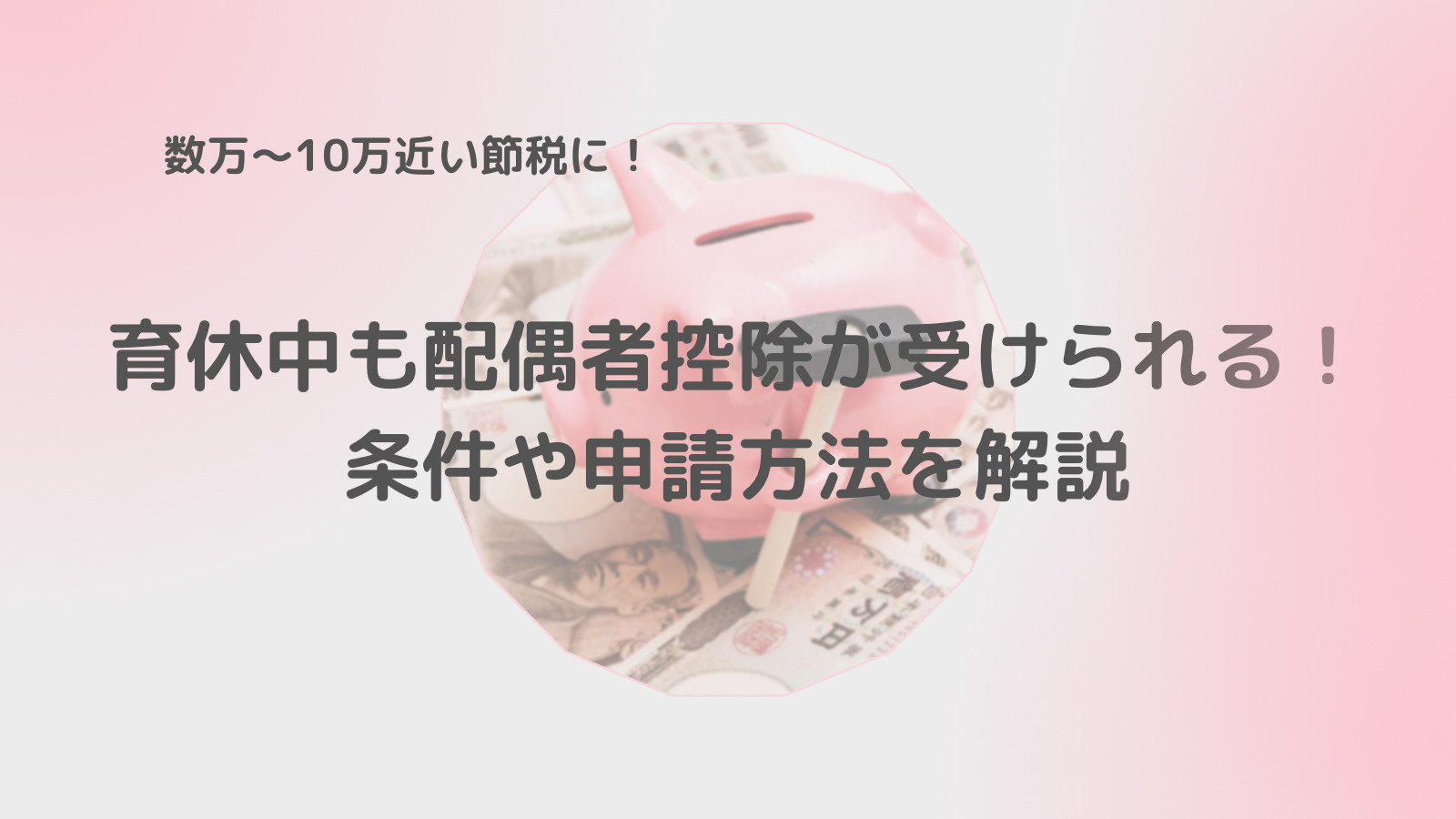こんにちは!育休中ママのみゆです。
- 育休中は手当が出るけれど、収入が減って家計管理が大変…
- 育休を1年以上とっているから手当もなくなってしまった…
そんな育休中のママは多いのではないでしょうか。
産休・育休中は出産手当金や育児休業給付金などが支給されますが、働いていたときからは収入は減少します。
育児休業給付金は原則として子どもが1歳になるまでの支給となるので、1年以上育休をとっていれば以降は収入がない状態になります。
我が家も1年以上育休をとっているので、私自身の収入はない状態です。
そんなときに利用できるのが、「配偶者控除」です。
育休中でも収入が201万円以下であれば「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を申請することができ、払いすぎていた税金を返してもらうことができます。
個々の家庭の状況により異なりますが、申請すれば数万円、もしかしたら10万円近いお金が返ってくるかもしれません。
この記事では育休中の配偶者控除について、
- 配偶者控除とは何か?
- いくらお金が返ってくるのか?
- どうやって申請すればいいのか?
といったことについて詳しく解説していきます。
育休中だけれどまだ配偶者控除を申請していない、という方はこの記事を読んでぜひ申請してみてください!

本来払わなくてもいいはずだったお金が戻ってきますよ♪
そもそも控除ってなに?

「控除」とは差し引くことを意味する言葉で、税金を計算する際に用いられます。
税金は年収ではなく課税所得に対してかかります。
会社員の場合、課税所得の簡単な計算式は以下の通りです。
課税所得 = 年収 - 控除
一方、税金の計算式は以下の通りです。
税金 = 課税所得 × 税率
=(年収-控除)× 税率
つまり、控除(年収から引かれる額)が増えれば、税金の額を減らすことができるのです。
配偶者控除とは?

配偶者控除は所得控除の一つで、簡単に言うと「収入が少ない配偶者がいる場合は税金を安くしてあげよう」という制度です。
配偶者控除を受けられるのは配偶者ではなく納税者本人です。
つまり妻が育休中の場合、夫が配偶者控除を申請するということになります。
配偶者控除を受けられる条件は?
配偶者控除を受けられる条件は以下の5つです。
①12月31日時点で戸籍上の夫婦であること
②夫婦で生計を一にしている(=同じ財布から生活費を出している)
③事業専従者として給与をもらっていないこと(親が自営業でその仕事を手伝っているなど)
④本人の年間収入1,195万円以下(所得1,000万円以下)
⑤配偶者の年間収入103万円以下(所得48万円以下)
この5つすべてに当てはまる場合に配偶者控除が受けられます。
出産手当金や育児休業給付金の取り扱いは?
産休・育休中にもらえる手当には、主に「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付金」があります。
実はこれらの手当は全て非課税なので、所得金額には含めません。
なので条件で示した配偶者の年間収入(所得)は手当を除く、勤務先などからもらえる給料のみで計算します。
収入103万円を超えたら控除は受けられないの?
収入が103万円を超えている場合でも、収入201万円以下であれば「配偶者特別控除」が受けられます。
この制度では、配偶者控除よりも配偶者の収入の条件が緩和されています。
収入以外の条件は配偶者控除で示した①~④と同じで、それに加えて以下の場合受けることができます。
配偶者の年間収入103万円以上、201万円以下(所得48万円以上、133万円以下)
控除額は配偶者特別控除よりは少なく、収入が高くなるほど控除額は減っていきます。
受けられる控除の額は?
控除の額は、以下の表の通りです。
配偶者控除
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
配偶者特別控除
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | |||
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
| 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除でいくら戻ってくる?

申請することでいくら税金が戻ってくるのかは気になるところですね。
戻ってくるのは「所得税」と「住民税」です。
また上の子が保育園に通っている場合、保育料が安くなることもあります。
所得税はいくら戻ってくる?
簡単な計算では「控除額×税率=戻ってくる額」となります。
所得税は所得額により税率が異なります。
例えば年収500万円、税率10%、控除額38万円とすると、戻ってくるのは「38×0.1=3.8万円」です。
自分達の税率がどれくらいか気になる方は、国税庁のサイトで一度確認してみてください。

参考までに、我が家の所得税還付金額は38,741円でした。
住民税はいくら戻ってくる?
上記した控除の額は所得税の場合であり、住民税では控除額が異なります。
住民税の控除額は33万円です。住民税は基本一律10%なので、戻ってくるのは「33×0.1=3.3万円」です。
上記の例で考えると、所得税と住民税の返ってくる額を合計すると、「3.8+3.3=7.1万円」になります。
この金額はあくまで目安で各家庭の状況により詳しくは異なりますが、戻ってくるとうれしい金額になりそうですね!
保育料は安くなるの?
保育料は「市町村民税所得割」に応じて設定されています。
この所得割は課税所得から計算されるので、
控除が増える → 課税所得が減る → 市町村民税所得割も減る
ということになり、保育料の階層区分が変われば保育料が減額になる場合もあります。
保育料は市町村によって大きく異なるので目安の額は明言できませんが、減額される可能性もあるということは覚えておきましょう。
3歳以上で保育料が無償化になっていても、給食費が安くなることもあります。
どうやって申請する?

配偶者控除の申請方法は主に以下の方法があります。
年末調整で申請する
これが一番簡単な方法です。
年末調整の際、以下の2つの書類を記入して会社に提出します。
①配偶者控除申告書
②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②については、今年分と来年分の2枚分があります。来年度分については、来年も育休をとり収入が201万円以下になると予想される場合、記入しておきましょう。
詳しい記入方法については、下記の国税庁ホームページを参考にしてください。
参考:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁
確定申告で申請する
年末調整で申請ができなかった場合や自営業の方の場合は、確定申告を行います。
確定申告は、基本的に翌年の2月16日~3月15日の期間で申請を受け付けています。
マイナンバーカードを持っている方、以前確定申告をしていてID・パスワードを設定している方はスマホで申請を行うことができます。

我が家はマイナンバーカードもIDもなかったので、パソコンで作成した申告書を印刷し、直接税務署に提出しました。
申請に必要なものは以下の通りです。
・申請者、配偶者両方の源泉徴収票
・子どもを含む、家族全員のマイナンバーがわかるもの
・申請者本人名義の銀行口座がわかるもの(還付金受け取り用)
源泉徴収票は提出する必要はないので、それぞれの収入などの情報がわかれば大丈夫です。
還付金は銀行口座への振り込みと、ゆうちょ銀行の各店舗または郵便局窓口での受け取りを選択することができました。
銀行振り込みについては一部ネット銀行では対応していないこともあるそうなので、ネット銀行への振り込みを希望する場合は銀行に還付金の受け取りが可能か確認が必要です。
また郵送や直接の提出の場合は、本人確認書類の写しを添付します。
5年以内であれば還付申告をすることも可能
年末調整や確定申告で申請し忘れていた、以前育休をとっていたけれど申請していなかった、という方は5年以内であればぜひ還付申告をしてみてください。
還付申告についても、申請方法は確定申告とほぼ同じです。
ただし、所得税や住民税は還付申告すれば返ってきますが、保育料については以前の分を遡って返してもらえるかどうかは自治体によって異なるようです。
保育料もかえってくるのか気になる場合は、一度自治体に確認してみてください。
まとめ:育休中は配偶者控除を使って節税しよう!
以上、育休中の配偶者控除について解説しました。
ポイントをまとめると以下の通りです。
- 本人の年収が1,195万円以下/配偶者の年収が103万円以下であれば「配偶者控除」が受けられる
- 年収が103万円を超えている場合でも、年収201万円以下であれば「配偶者特別控除」が受けられる
- 配偶者控除で返ってくるのは所得税と住民税。保育料が安くなる場合もある。
- 申請は年末調整または確定申告で行う。5年以内であれば還付申告も可能。
育休中は収入が減りますが、赤ちゃんの誕生で何かとお金がかかるもの。
使える制度は上手に利用して、節税して返ってきたお金を有効活用できるといいですね!

ご覧いただきありがとうございました♪